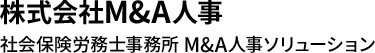2013年12月28日
2013.12.28
日本企業における定額残業代導入の歴史
企業経営をしていく上で常に思いをめぐらせることは、2つです。ひとつは、売上をどのように維持・向上させ続けるかという営業・マーケティングサイドの戦略、そしてもうひとつは、コスト構造をどう改善して利益を出せる筋肉質の社内体制を作るかということです。
原価コストのうち、多くの業種で最も大きな割合を占める部分が人件費です。経営者は、常に人件費の効率的な管理を頭のどこかで考えているはずです。ところが同じコストでも、人件費は感情を持ったヒトに関するコストという側面があり、ただ闇雲に減らせば良いというものでないことは明らかです。
合理的な理由なく人件費を減らせば、社員のモチベーションが下がり、他の条件の良い企業に転職してしまうかもしれません。逆に多少の人件費増を受け入れて、上手に社員を鼓舞することで、売り上げ増に結び付く素晴らしい働きをしてくれる可能性もあります。
理想としては、売り上げ増を伴った人件費の増加(給与の増加)が、労使ともに持続的に成長できる姿であると思いますが、なかなか上手くいかないことも多いのが現実であろうと思います。
そういった環境の中で登場したのが、定額残業代です。年俸や基本給の一部を定額残業代とするタイプや、定額残業手当として年俸や基本給とは別に支給するタイプがあることは、過去のブログでも触れた通りです。基本的には、残業代を青天井で払いたくないという人件費管理の観点から導入されたというのが、実態かと思います。
こういった定額残業代に対して、昭和の頃は、就業規則や雇用契約書に定額残業代の定めがあり、労働基準法所定の計算方法で客観的にその額を計算できれば、有効であると解釈する裁判例が出ていました。
この流れを受け、平成に入ってから徐々に、就業規則や雇用契約書に定額残業代の金額を計算できるように定めるケースが増えてきたという状況があります。
そして、就業規則や雇用契約書で定額残業代を基本給とは別の手当として定め、かつ、法定の計算方法で額を計算できれば、一定の確率で、有効であると判断される裁判上の流れが最近まで続いていました。ところが、昨年末あたりから、この流れに変化が起きているようなのです。
以下、今月行われた弁護士先生の講演から得た情報を元に要点をまとめてお伝えさせて頂きます。ここで記載することは、経営者にとっては最も厳しい対応を求める最高裁裁判官のスタンスであり、全ての裁判において必ず適用されるというものではありません。
しかし、定額残業代に対する裁判官の姿勢は、この裁判の後、明らかに流れが変わったということですので、これからのリスクマネジメントとしては、今までよりもさらに一歩踏み込んだ対応が求められる時代が到来したのかもしれません。
第二次定額残業代時代の到来
この流れの変化を捉えて講演された弁護士先生は、「第二次定額残業代時代」が到来したと警鐘を鳴らしています。第一次定額残業代時代とは、多くの企業が、就業規則などに定額残業代の定めをしていなかった時代を指します。
その中で、しっかりと定めをしておけば、裁判で有効と判断され得た時代ということになります。昭和から平成の初期までが、この時代に当たるのではないかと思います。
その中で、しっかりと定めをしておけば、裁判で有効と判断され得た時代ということになります。昭和から平成の初期までが、この時代に当たるのではないかと思います。
その後、過渡期的な時期があり、去年辺りから、第二次定額残業代時代に突入したようだ、というのが現役弁護士としての実感値ということです。第二次定額残業代時代とは、就業規則や雇用契約書に定額残業代の定めをしていたとしても、裁判で否決される傾向が定着した時代、ということが言えそうです。
就業規則にも定額残業代の明確な定め(含まれる残業時間数など)の記載がない会社は、間違いなく裁判で否認される時代ですが、今後は、就業規則・雇用契約書等に明確に時間数を定めていても、安心できない時代になったようです。
下級審の考え方に影響を与えた(?)テックジャパン事件
これは以前のブログでも触れた判例ですが、平成24年3月8日の最高裁判決で、定額残業代について、櫻井最高裁裁判官による以下の補足意見が付されました。これは、あくまでも補足意見であって法的な拘束力はないものと言えますが、その後の裁判官の考え方に実質的な影響を与えている可能性があるというのが、現役弁護士の見方です。
その補足意見の重要部分を以下に引用します。
—————————————————————————————————————————————–
—————————————————————————————————————————————–
(引用開始)
便宜的に毎月の給与の中にあらかじめ一定時間(例えば10時間分)の残業手当が算入されているものとして給与が支払われている事例も見られるが、その場合は、その旨が雇用契約上も明確にされていなければならないと同時に、支給時に支給対象の時間外労働の時間数と残業手当の額が労働者に明示されていなければならないであろう。さらには10時間を超えて残業が行われた場合には、当然その所定の支給日に別途上乗せして残業手当を支給する旨もあらかじめ明らかにされていなければならないと解すべきと思われる。本件の場合、そのようなあらかじめの合意も支給実態も認められない。
——————————————————————————————————————————————
(引用終了)
(引用終了)
二行目の「支給時に」以下の部分は、毎月の給与明細書で、時間外労働の時間数と残業手当の額が明示される必要があるということを言っています。
また、最後の行の「支給実態」とは、就業規則や雇用契約書で、固定残業代を超える残業代は別途支払う旨の定めをしているだけでは不充分で、実際の支給実態が伴っていなければ裁判では認めるべきではないという意見となっています。
また、最後の行の「支給実態」とは、就業規則や雇用契約書で、固定残業代を超える残業代は別途支払う旨の定めをしているだけでは不充分で、実際の支給実態が伴っていなければ裁判では認めるべきではないという意見となっています。
あくまでも補足意見であって、最高裁の公式見解としては採用されなかったということになっているものの、ブラック企業が跋扈する世の中ですので、裁判所は、定額残業代に対しても、違法な人件費の削減手法として活用されていないか目を光らせていると考えた方が良いと思います。
この判決以降の東京地裁・横浜地裁の下級審判決の趣旨は、前述の櫻井裁判官の補足意見に近いものが続出しているということです。しかも、とても速いスピード結審だそうです。これからの裁判の動向を注視していく必要がありますが、やはり定額残業代の裁判は、新しい時代に入ったとみておいたほうが良さそうです。
当事務所でのこれまでのアドバイスも、ここまで踏み込んではおらず、就業規則や雇用契約書に定額残業代の含まれる時間数、計算方法を明記してくださいというところまでしかしてきていませんでしたが、リスクマネジメントの観点から、さらに一歩踏み込んだ対応を検討する必要があると考えています。
当事務所でのこれまでのアドバイスも、ここまで踏み込んではおらず、就業規則や雇用契約書に定額残業代の含まれる時間数、計算方法を明記してくださいというところまでしかしてきていませんでしたが、リスクマネジメントの観点から、さらに一歩踏み込んだ対応を検討する必要があると考えています。