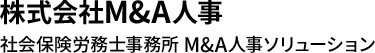2014年05月25日
2014.5.25
会社は、労働基準法により、社員の労働時間を管理・記録する義務を負っていますが、一定の条件に当てはまれば、その義務を免除され、所定の労働時間もしくはその仕事に通常必要とされる時間を労働したものとみなすことができる制度があります。それが事業場外のみなし労働時間制と呼ばれるもので、労働基準法に定められているものです。
ここでいう一定の条件とは2つあります。ひとつは、使用者の指揮命令権が及ばないことであり、もうひとつは、その結果として、実際の労働時間を算定することが困難であることです。
一般的には、外回りの営業職や出張時に適用することとしている会社が多いと思います。これまでのコンサルティング経験を振り返ってみても、相当数の会社がこの制度を活用しているものと思われます。統計数値をみると、厚生労働省の就労条件総合調査(2013年度)では、大企業ほど導入率が高く、1,000人以上企業で17.7%、30~99人規模企業で7.7%の導入率となっています。(表1)
(表1)厚生労働省「就労条件総合調査」(2013年度)
|
企業規模/年度 |
30~99人 |
100~299人 |
300~999人 |
1,000人以上 |
|
2010 |
7.5 |
11.2 |
17.5 |
19.7 |
|
2011 |
7.6 |
11.8 |
18.7 |
19.0 |
|
2012 |
8.7 |
13.1 |
19.0 |
17.1 |
|
2013 |
7.7 |
11.4 |
17.6 |
17.7 |
厚生労働省の統計は、実務上の感覚よりもだいぶ低い導入率になっていますが、職種別に統計値を出している中央労働委員会の以下の統計の方が、実態を表しているのではないかと思われます。(表2)
(表2)中労委「労働時間・休日・休暇調査」(2008年)
|
産業/職種 |
実施率 % |
本社 |
管理事務 |
販売営業 |
情報処理 |
研究開発 |
生産 |
対人 サービス |
|
産業計 |
31.3 |
4.5 |
7.6 |
66.7 |
4.5 |
4.5 |
1.5 |
1.5 |
|
製造業 |
41.0 |
5.3 |
8.8 |
71.9 |
3.5 |
5.3 |
1.8 |
1.8 |
この中労委の調査委結果によると、外回りが多いと想定される営業職での導入割合が圧倒的に高いことが分かります。この導入率の水準は、実際の実務での感覚ともかなり近いものがあります。
直行直帰で会社事務所に立ち寄らない働き方を認めている会社では、この制度を活用しているところが多いでしょう。ただ中には、営業職というだけで、実際の働き方に関わらず制度を導入している会社も少なからず存在しているのが実態ではないかと思われます。
この制度を適用することで、仮に一日12時間働いたとしても、会社としては、「指揮監督権が及ばず、労働時間が算定できない」ということで、通常の所定労働時間(たとえば一日8時間)勤務したとみなせるという制度であるため、本来、時間外労働(残業)手当の支給が必要であるべきところ、会社は、その支給義務を免れることもできる制度ともいえます。もちろん、常に一日12時間程度働かないと業務を完遂できないという労使間の合意があれば、一日8時間ではなく12時間分の賃金を支払うという労使協定を結ぶことはありますが、実際には、「一日の所定労働時間を勤務したものとみなす。」として、賃金を上乗せして支払うケースは、かなり少ないのが実情でしょう。
逆に求められる成果や営業先訪問数などを短時間でこなせるようであれば、所定労働時間未満しか働かなくても、「所定労働時間は勤務したものとみなされて」賃金は減らされません。器用な社員にとっては、うまく活用すればワークライフバランスを維持しながら、働くこともできなくはないといえます。
経営者としては、明らかな長時間労働の実態がない限り、残業代の支払い増につながるようなことはしたくないですから、「所定労働時間を勤務したものとみなす」ということを就業規則に規定することが多くなります。
こういった背景から営業職を中心に広く活用されている事業場外みなし労働時間制ですが、最近、注目の判例が出ました。旅行会社の添乗員に対する事業場外のみなし労働時間制が、「適切ではない」として否認されたものです。本件の裁判所の基本的な考え方が、営業職のみなし制適用の妥当性の検証にも役立つと思いますので、以下に概要とポイントをまとめてお知らせします。
まずは、日経新聞にも記載された判例の要旨を引用しますので、ご覧ください。
(引用開始)
———————————————————————————————————-
———————————————————————————————————-
添乗員、みなし労働認めず~最高裁判断 残業代支払確定~
海外旅行の添乗員について、労働時間の算定が困難な場合に一定時間働いたとみなす「みなし労働時間制」を適用するのは不当として、派遣添乗員の女性が未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第二小法廷は24日、「労働時間算定が困難とは言えない」との判断を示した。
被告の阪急トラベルサポート(大阪市)側の上告を棄却。添乗員の女性の「みなし労働時間制」の適用を認めず、同社に約30万円の支払いを命じた二審・東京高裁判決が確定した。
最高裁は、みなし労働制が適用されるかどうかについて「業務の性質、内容や状況、指示や報告の方法などから判断すべき」と指摘。今回のケースでは、会社はあらかじめ旅程管理に関して具体的な指示をしており、ツアー中も国際電話用の携帯電話を貸与していたほか、終了後は日報で詳細な報告を受けていたことなどから、「労働時間の算定が困難とはいえない」と結論付けた。
———————————————————————————————————-
———————————————————————————————————-
(引用終了)
この最高裁の判決内容を先に触れた2つの条件の観点から分解すると、以下のようになります。
① 使用者の指揮監督をうけていないか?
実際に上司が同行しているわけではないので、逐一監視されている状況ではありませんが、海外ツアー中も、会社から支給された業務用の携帯電話を所持しており、いつでも会社から連絡を入れて指示することが可能な状況であったことから、使用者の指揮監督を受けていないという条件に当てはまらないという判断をされたようです。さらに、新聞には出ていませんでしたが、携帯電話の電源は常にオンにしておくことなど、具体的な指示も出ていたことから、指揮監督権に関する条件は、完全に否認されました。
② 実際の労働時間が算定困難であるか?
添乗員は、詳細な業務日報をツアー終了後に提出することが義務付けられていたということで、その日報の内容は、旅程表の訪問場所やホテルなどの発着時刻を詳細に記入することが求められていました。裁判所は、これを信頼に値する情報と位置づけ、労働時間算定の補助資料として活用することが可能と結論付けました。
もともと事業場外のみなし労働時間制に関する訴訟では、会社が敗訴する確率が相当高かったというこれまでの経緯があり、今回の一件でその流れは決定的になったと業界では言われています。
すでに同制度を適用している会社では、再一度運用実態の点検をされることをお薦めします。特に営業職を想定した関連通達も出ており、これに合致するような働き方が実現できていれば問題ありませんが、そうでない場合は、対策を考えておいた方が無難でしょう。
「事業場外労働に関する通達」
以下のような場合には、事業場外のみなし労働時間制は適用されません。
① 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合 ⇒ 使用者の指揮命令が及び、労働時間算定が可能と考えられる。
② 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル(古いですね。。。)等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合 ⇒ いまやスマホの時代ですので、適宜連絡を取りながら社外で業務を遂行する場合、労働時間の算定が困難とは認められないケースがほとんどでしょう。
③ 事業場において、訪問先、帰社時刻等の業務の具体的指示を受けた後、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合 ⇒ 業務の遂行の詳細について、使用者の具体的指示があると解され、同制度の適用は認められません。
こうしてみてきますと、現在のビジネス環境でこの制度の適用が認められるのは、とてもハードルが高いように見えますし、実際、事業場外労働のみなし労働時間制は「死んだ」(実際に活用できる余地がなくなったという意味)と公言する弁護士先生もおられます。
もちろん訴訟にならなければ、あくまでも潜在的なリスクということではありますが、一度表面化すれば、過去の残業代の支払いに話が及びますので、もし長時間労働の実態がある中でこの制度を適用しているような場合は、営業体制やビジネスフローの見直しが第一ですが、一日のみなし労働時間を現状よりも長めに設定するなど、制度運用と実態を近づける努力も必要ではないかと思います。ひいてはそれが将来のリスクヘッジにもなると考えれば、投資効率という観点でも悪くないのではないかと思います。
訴訟にならずとも、労基署の調査が入った場合は、前述の通達や今回紹介した判例の観点を踏まえた指導が行われますので、日頃の管理をしっかり行うのに越したことはないと思います。