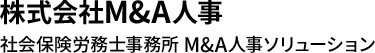2013年12月26日
2013.12.26
労働基準法第16条は、賠償予定を禁止しています。その趣旨は、労働契約の不履行などに対して損害賠償額を定めることを認めてしまうと、労働者の自由意思を不当に拘束して、労働者の足止め策として利用されるなど弊害を生じるリスクがあるため、法律で禁止しているものです。
実際の条文は、以下の通り定められています。
「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」
(労働基準法第16条)
(労働基準法第16条)
ここでいう違約金とは、契約の不履行者がその相手に対して支払う金銭のことで、実際に損害が生じる・生じないに関わらず取り立てることができるものと考えられます。労働者の退職を抑制する効果を狙って違約金の定めをする会社がみられますが、法律上は認められていません。
この違約金の代表的なものが、会社が費用負担をした海外の大学への留学費用の返還に関する取り決めです。将来の幹部候補である社員を、海外の大学のMBAコースに派遣するような場合、帰国後数年以内に退職した場合は、会社が負担した授業料等を返還させる旨を就業規則に定めている事例があります。
たとえば、以下の判例が参考になります。「留学終了後5年以内に自己都合により退職した時は、原則として留学に要した費用を全額返還させる旨の規程は、海外留学後の会社への勤務を確保することを目的とし、自己都合で退職するものに対する制裁の意味合いを有するものであるから、労働基準法16条に違反し、無効である。(平成10.9.25 東京地裁 新日本証券事件)労基法上の違約金の定めであると判断されれば、無効となるリスクがあるということです。
一方、同じ海外留学費用に関する定めでも、有効と判断される場合もあります。留学費用の返還に関する定めが違約金の定めとはみなされないケースです。いくつかの判例で共通して検討ポイントに挙げられているのは、以下の点です。
(1) 業務との関連性がどの程度あるか?
労働契約の不履行に対して違約金を定めることが労働基準法違反となるのであって、海外留学自体が業務との関連性が低い場合は、そもそも労働契約の不履行に当たらないと判断される傾向があります。留学への応募が本人の意思であって、留学する学部や科目の選択などが本人の自由意思に任されているような場合は、業務とみなされない傾向がみられます。
将来の幹部候補生を長期的な育成の観点から海外留学させるような場合で、対象者を指名して会社が留学させるのではなく、本人が制度に応募して留学するような場合は、業務との関連性が認められない可能性が高いでしょう。そうすると、「労働契約の不履行」に対する違約金という捉え方が困難になるため、会社にとっては有利な材料になっています。
一方、海外留学ではなく、業務に関連した海外研修制度のための費用の返還を定めたものは、違約金の定めに当たるとして無効とされた判例があります。(平成10.3.17 東京地裁 富士重工業事件)
(2) 留学費用返還の誓約書はあるか?
海外留学費用の返還に関する誓約書がある場合、金銭消費貸借契約結ばれているとみなされ、費用の負担はその契約内容によって規定されるべきであり、労働契約の不履行によって費用負担が決まるものではない、という考え方があります。
その場合、留学から帰国後、退職せずに一定期間が経過すれば、費用の返済債務が免除されるという金銭貸付の契約と判断される傾向があります。つまり、「貸付金を契約内容に従って返還してください。」ということになるので、労基法上の違約金ということではなくなるというわけです。
上記の論点に関しては、野村証券事件(平成14.416 東京地裁)、明治生命保険事件(平成16.1.26 東京地裁)、長谷工コーポレーション事件(平成9.5.26 東京地裁)などが参考になります。
こういった判例における論点を踏まえて、業務と関連性が低く、業務命令ではなく本人希望で留学させるような場合は、万一社員が帰国後すぐに退職した場合でも、貸付金の返還請求として有効となる可能性があります。
ところで、様々な会社の就業規則等をみていると、違約金に該当するのではないかと思われる事例に時々遭遇します。最近見た中では、地方拠点・工場等への転勤に際して支給される支度金、住宅費補助、単身赴任の場合は帰省旅費等まで含めて、一定年数以内に退職した場合は、返還させるという規定がありました。
まだ検討段階の規程ということでしたが、違約金として無効になる可能性が高いので、再検討をお薦めしましたが、その会社とは、直接その点についてアドバイザリー契約をすることはありませんでしたので、その後の展開がどうなったかは分かりません。
もう一つ上げると、教育訓練に係る補助費用について、やはり一定年数以内に退職した場合は、返還させるという規定でした。これは、どう判断されるか分かりませんが、教育訓練の内容が業務と直接関連性が低いもの、例えば語学の研修などであって、金額も少額なものであれば、有効と判断される余地があるかもしれません。その場合の判断基準は、実質的に、退職を抑制する足止め策として効果が認められるかどうかということかと思います。
実費以下の費用補助であって、金額が少額であり、立替金と解される場合は、有効と判断されたケースもあります。最終的には、個別事例ごとの判断ということになりますが、表面的な部分だけを真似して、こんなはずではなかったということがないように、留意されて事を運ぶ必要がありそうですね。