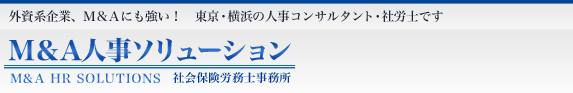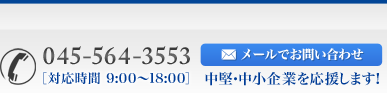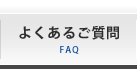労務コンサルティング
就業規則の作成・改定
組織を守り、かつ、社員が活き活きするルール作りを目指します
就業規則は、労務リスク&人材マネジメントツールとして活用しましょう
そもそも就業規則とは何か?
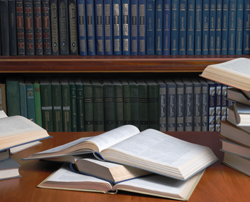 就業規則は、文字通り、職場の就業に関してのルールを定めたものですが、実際には、採用や退職手続き、服務規律などを定めた本則、給与や時間外労働(残業)について定めた給与規程に始まり、その他多くの付属規程から成ります。代表的な附属規程には、慶弔見舞金規程、出張旅費規程、社宅管理規程、退職金・年金規程、育児・介護休業規程などがあります。これらは、社員の給与、福利厚生、退職給付について定めており、
就業規則は、文字通り、職場の就業に関してのルールを定めたものですが、実際には、採用や退職手続き、服務規律などを定めた本則、給与や時間外労働(残業)について定めた給与規程に始まり、その他多くの付属規程から成ります。代表的な附属規程には、慶弔見舞金規程、出張旅費規程、社宅管理規程、退職金・年金規程、育児・介護休業規程などがあります。これらは、社員の給与、福利厚生、退職給付について定めており、規程の作り方によっては、人件費に与える影響は決して小さくありません。
また、採用、退職等のトラブル発生時における効力も大きく変わってきます。
定期的な見直しをお薦めします
法令が頻繁に変わる近年の状況で、古い規定を放置しておくことは、法令順守と労務リスクマネジメントの問題があるだけでなく、会社と社員の間の信頼関係も揺らぎかねません。インターネットで簡単に情報を入手できる現在、社員のほうが法令を良く知っているという状況もあり得ます。最新の法令への定期的なアップデートは社員の信頼感を維持するためにも必要です。またリスクマネジメントの観点から、最新判例の動向も踏まえた規程内容としておくことも、経営管理上の重要な施策と考えます。採用力の向上と退職リスクの最小化にも効果を発揮します
さらに、採用力の向上や、社員の退職リスクを最小化したい場合は、就業規則に記載される労働条件の他社比較・ベンチマークも合わせて実施することをお薦めします。競争力のある給与・賞与、福利厚生、退職金の内容と支給水準を把握した上で、労務リスクマネジメントも考慮した規程内容を実現することで、大切な人材の士気を維持しつつ、長く勤めてもらえる可能性が高まります。労務リスク管理はもちろんのこと、良質な人材マネジメントによる生産性の向上(人材の採用力向上、モチベーションアップ、退職率の低減等)を目指す経営者・人事担当者様は、是非当社の就業規則作成・改定サービスをご活用ください。
基本サービス内容(就業規則の作成支援)
会社の経営・人事戦略に応じた就業規則の作成を支援します
業種・規模・ビジネスシナリオ次第で、大きく異なる就業規則の内容
様々な状況に応じて最適の就業規則をご提案します
 就業規則は、人事労務管理に関する会社の基本ルールです。労働基準法に定められた絶対的必要記載事項は必ず定める必要がありますが、その内容は会社によって異なることが普通です。また、法令で定めることを求められていない内容についても必要に応じて規定化しておくことが望ましいものもあります。
就業規則は、人事労務管理に関する会社の基本ルールです。労働基準法に定められた絶対的必要記載事項は必ず定める必要がありますが、その内容は会社によって異なることが普通です。また、法令で定めることを求められていない内容についても必要に応じて規定化しておくことが望ましいものもあります。絶対的必要記載事項は、労働時間や賃金の支払い方などの基本的な労働条件ですが、業種や職種によっては、変形労働時間制や裁量労働制、事業場外のみなし労働時間制などを活用することもあり、これらの制度を導入するためには、状況により労使協定などの締結と届出、あるいは、労使委員会の設置と運用などが必要になります。就業規則の定めに付随して発生する事項も含めて適切に対応することが必要です。
また、就業規則に一般的に規定される福利厚生的なものは、社員の長期定着率を高めたり、会社との一体感を維持する観点から重要な要素です。福利厚生に関する規定を定める際は、市場プラクティスの動向や支給水準を的確に押さえた上で、自社の規定内容を設定するプロセスが欠かせません。
一方、法令で求められていない事項で重要なものに、リスクマネジメント系の規定があります。これは就業規則に定めていなくても法令上、特に咎めはなく、また、社員のモチベーションへの影響も目に見えてありませんが、万一訴訟になった時に、会社を守るために重要となる規定です。
当事務所では、様々な業種・規模の会社の就業規則の作成・改訂を通じて培ったノウハウを活用し、貴社に最適の就業規則をご提案いたします。
就業規則作成サービスの内容
当事務所では、クライアント企業の要望に応じて、様々な就業規則作成のアプローチをご提案しています。ここでは、一般的な就業規則の作成・改訂プロセスをご紹介します。
1. 人事労務管理の実態と課題の把握
はじめに就業規則の全体を確認した上で、クライアント企業の人事労務管理の実態をヒアリングさせて頂きます。この段階で、規程の内容と実際の運用が異なっていることが判明する場合が極めて多いのが実情です。規定内容と実際の運用の格差となぜそのような状況になっているのかの背景を押さえ、以下の検討作業に進みます。
2. 最新の法令に応じたアップデート
大手の企業では、過去の就業規則の改訂時期と改訂内容を記録として残していることが普通ですが、中堅・中小企業では、数年間も規程を見直していないということも決して珍しくありません。昨今は、労働契約法、パートタイム労働法、育児・介護休業法などなど、実に多くの労働関連法規が頻繁に改正されているため、定期的に最新の法令への対応状況を確認する必要があります。
3. 訴訟時のリスクヘッジ対応
万一、社員が会社を訴えた場合、就業規則にどのような規定がなされているかは、裁判において極めて重要視されます。残業代の未払いやメンタルヘルス対応、休職者の扱い、降格、解雇、個人情報など・・・、様々な事柄で会社が訴えられる可能性がある状況で、就業規則に適切な定めがあるかないかが勝敗の分け目になることも少なくありません。
4. 人材マネジメント上の観点からの対応
就業規則に記載される処遇的なものは、給与以外にも結構たくさんあります。出張時の日当、社宅の貸与、各種補助金、報奨金制度、教育研修制度、リフレッシュ休暇、慶弔見舞金、生命保険や所得補償保険など、枚挙に暇がありません。自社の業界ポジショニングや戦略を踏まえた上で、これらの項目を他社とも比較して、総合的な観点から、適切な処遇水準を設定し、規程化しておくことが望ましい状況です。当事務所では、市場プラクティスのベンチマークから具体的な提案まで支援を行っています。
5. 就業規則案の最終化と社員説明会
法令対応、訴訟リスク対応、および、人材マネジメント上の対応が一通り終了したら、就業規則・付属規程一式を最終化し、社員説明会を開きます。従業員代表の意見を聴取した後、必要な労使協定等と合わせて就業規則を届け出ます。当事務所では、社員説明会へ向けた準備、および、説明会での質疑応答支援、労基署への届出まで全て対応させて頂くことが可能です。
※取り敢えずシンプルに作りたい場合から、完全カスタマイズの場合まで、貴社の状況に応じてオーダーメイドのご提案をいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
時間外労働マネジメント
人件費管理とモチベーション維持の両立を目指して支援します
残業の適切な管理を通じ、人件費最適化とモチベーション維持を同時に実現
労働基準法の時間外労働(残業)は、戦前の工場労働者を想定していた
 様々な雇用形態、職種、働き方が混在する今日、時間外労働(残業)の適切な管理は、人件費に影響があることはもちろんですが、就業規則の定め方や残業指示を含む運用のあり方が、社員のモチベーションに大きく影響を与えます。その結果、業務の生産性も大きく左右される可能性があります。たとえば、残業の「定額・前払い制」を導入する会社が増えています。また、給与体系の中の諸手当の定め方や給与と賞与の配分、振替休日、代休ルール、残業指示のルールの設定の仕方などにより、
様々な雇用形態、職種、働き方が混在する今日、時間外労働(残業)の適切な管理は、人件費に影響があることはもちろんですが、就業規則の定め方や残業指示を含む運用のあり方が、社員のモチベーションに大きく影響を与えます。その結果、業務の生産性も大きく左右される可能性があります。たとえば、残業の「定額・前払い制」を導入する会社が増えています。また、給与体系の中の諸手当の定め方や給与と賞与の配分、振替休日、代休ルール、残業指示のルールの設定の仕方などにより、残業コストは大きく影響を受けます。
仕事が早い優秀社員は、残業手当が少なくなるという矛盾
同じ業務を任された二人の社員を想像してみましょう。作業の質が高くスピードも速いAさんは、定時に仕事を終わらせて所定の賃金を受け取る一方、Bさんは、定時に仕事が終わらず、残業手当を支給されます。結果として、「いい仕事」をしたAさんに対する賃金が、Bさんよりも低くなるという状況が生じます。これは、単純な一例ですが、日常の人事マネジメントを振り返ると、似たような現象が思い当たるのではないでしょうか?貢献度と給与を適切に関係づけることは、社員の生産性・モチベーションに少なからぬ影響を及ぼします。残業手当に関する課題を抱えた組織は少なくありませんが、残業の定額・前払い制の検討も含めて、人事制度全体を通じた貢献度に応じた処遇体系の整備を進めることが、より大きな経営課題と言えます。様々な職種に応じた働き方の活用
一日8時間、一週40時間を超える労働は、原則として、残業手当を支給しなければなりません。但し、事業ニーズに沿った様々な働き方を組み合わせることで、コストを抑えることも可能です。業務の繁閑に応じて労働時間を変動させられる変形労働時間制や、成果に応じた処遇を前提とする裁量労働制、営業職の事業場外みなし労働時間制などを活用し、最適な働き方を提案することができます。同時に、残業代の削減効果も期待でき、生産性の高い社員へ賞与でより厚く報いることも可能になります。残業代の抑制のみを目的とする施策は一時的な効果はありますが、持続性は見込めません。持続的な事業の成長を実現するためには、人材の潜在力を最大限発揮させる総合的な施策が求められます。費用対効果の最大化と同時に従業員の士気向上を実現したい経営者・人事ご担当者様は、是非当事務所のサービスをご活用ください。
労務管理アドバイザリー
最新法令対応の市場プラクティスを含めたアドバイザリーを提供します
最新の法令対応や適切な実務プロセスを全力サポート
頻繁に行われる法改正の対応実務を迅速・丁寧にサポート

過去数年だけでも、同一労働同一賃金関連法、副業の解禁、無期雇用転換権、労働条件明示ルールや育児休業法の改正など、様々な法改正や指針が出されており、全てにおいて適切な実務運用を行っていくことは容易ではありません。多くの顧問先企業様と日々接している当事務所だからこそ提供できる現場感を含めた市場動向情報の提供も含めて、法改正対応の運用実務を強力にサポートします。
メンタルヘルス対応、休職規程の整備
様々な人材が協働する中で、メンタル面の不調を訴える従業員が増え続けています。社会的な要因、会社の要因および個人的な要因が複合的に絡み合い今日の状況を作り出しているものと思われますが、大切な人材が再び健常時のパフォーマンスを発揮できるように、休職を含めたプロセスを適切にマネジメントすることが求められます。センシティブな対応が求められる領域であり、特に日本人の人事担当者が不在の外資系企業においては、アジアリージョンの人事担当を強力にバックアップいたします。