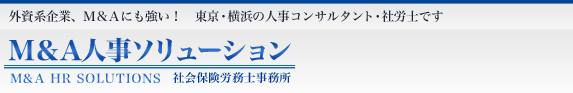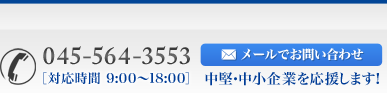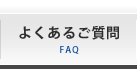M&A人事コンサルティング
人事デューデリジェンス
対象企業の組織・人事領域を財務・非財務的な観点の双方から検証します
「価格への反映支援」と「PMI人事マネジメントの課題明確化」を通じ、
期待効果の実現を支援します
なぜ、人事デューデリジェンスが必要なのでしょうか?
 M&Aに際し、ビジネス、財務、法務等のデューデリジェンスが実施されます。では人事デューデリジェンス(人事DD)を実施しているケースは、どの程度あるでしょうか?近年、人事DDを実施するケースが増えているようですが、その目的は、買収価格の判断材料として退職給付債務を精査するものと考えている企業も少なくないようです。全ての案件で人事DDが必須ということではありませんが、人事DDを実施しなかったためにM&A後の期待効果が充分に実現できていないケースも少なくありません。
M&Aに際し、ビジネス、財務、法務等のデューデリジェンスが実施されます。では人事デューデリジェンス(人事DD)を実施しているケースは、どの程度あるでしょうか?近年、人事DDを実施するケースが増えているようですが、その目的は、買収価格の判断材料として退職給付債務を精査するものと考えている企業も少なくないようです。全ての案件で人事DDが必須ということではありませんが、人事DDを実施しなかったためにM&A後の期待効果が充分に実現できていないケースも少なくありません。
組織・人分野の理解不足が、期待効果を実現できない大きな要因
複数のコンサルティングファームの調査によると、M&Aの成功確率は3割程度で、その阻害要因の上位に組織と人に関するものが多くみられます。いずれも「組織文化の違い」が上位にランクされていますが、組織文化の形成要因は、経営方針、組織の権限や意思決定・伝達スタイル、社員の行動様式やモチベーションの状況、人事制度の特徴など、幅広い領域に及びます。数値として「見えない」ために敬遠されがちですが、人事DDを通じて包括的に精査することで、M&A後に必要となるアクションプランを作成し、適切な対応を優先順位を明確にして実行することが可能になります。
-当社の人事DDの特徴-
当社では、人件費の様々なシミュレーションに加え、組織運営や人事制度の特徴と運用実態、採用・退社の状況から未払い賃金や管理監督者問題を含む労務イシューまで、総合的な精査を実施しています。さらに、買い手企業の戦略を踏まえたPMI課題と対応の方向性について、優先順位と時間軸を含めて提示します。また、人件費の各種プロジェクションと契約書文言の検討にも迅速に対応しています。
基本サービス内容(人事デューデリジェンス)
目に見えない資産である「組織力と人」及び「人を支えるインフラ」を精査します
人事デューデリジェンスで人件費分析 + PMIの優先課題を抽出
PMIのシナリオを実現する組織・人材力を見極める
 人事デューデリジェンスでは、様々な観点から対象企業の組織と人に関する事項を精査していきますが、基本的には2つの観点から調査・分析を行います。まずは退職給付債務と人件費の分析です。これは買収価格に直接影響を与える項目ですので、当然重点的に調べます。もう一つは、財務以外の定性的な観点からの調査です。人材マネジメントの中心となる人事制度の仕組みと運用の実態に始まり、経営幹部を含む人材の質と退職リスクまで多岐に渡ります。
人事デューデリジェンスでは、様々な観点から対象企業の組織と人に関する事項を精査していきますが、基本的には2つの観点から調査・分析を行います。まずは退職給付債務と人件費の分析です。これは買収価格に直接影響を与える項目ですので、当然重点的に調べます。もう一つは、財務以外の定性的な観点からの調査です。人材マネジメントの中心となる人事制度の仕組みと運用の実態に始まり、経営幹部を含む人材の質と退職リスクまで多岐に渡ります。また、一口に人事デューデリジェンスといっても、案件により精査する範囲や分析の切り口は様々です。株式譲渡か事業譲渡か、あるいは、会社分割かというストラクチャーの違いや、買収者のPMI戦略上、対象会社・事業部門をどう位置付けているのか、組織の統合があるのかないのか、事業部門を買収して新会社を設立するのかなどのシナリオにより、報告する内容は全く異なります。
当事務所では、人事デューデリジェンスの豊富な支援実績で蓄積した知見を最大限に活用し、極めて限られた時間と制約のある情報開示の中で、クライアント企業の意向を的確に把握し、適正な買収価格算定のための基礎情報を提供します。また、買収後戦略の実行力を組織と人の観点から見極め、優先度の高い施策を含めて、最適なアドバイザリーをご提供致します。
人事デューデリジェンスの進め方
当事務所では、クライアント企業の要望に応じて、様々な支援形態にて対応しています。また、外資系企業に対しては、英語での報告書作成、経営陣との英語による討議、電話会議等も対応しています。ここでは、人事デューデリジェンスの標準的な進め方をご紹介します。
1. クライアント企業の戦略の確認
どのような経営戦略のもとでM&Aを検討していて、買収後にどのような経営を実行しようとしているのかをヒアリングを通じて把握します。人事デューデリジェンスの実行責任者が必ずしも全てを把握しているとは限りませんが、この段階での理解の深さが分析の質や重点精査領域の決定に影響しますので、可能な限りの情報を共有頂けるようお願いしています。対象企業によるマネジメント・プレゼンテーションが行われる場合は、クライアントの質問を通じて理解をより深めます。
2. 初期データリクエストの作成
買収の狙いとPMIの経営戦略を踏まえ、組織・人事領域で想定される課題を仮説ベースで構築します。構築した仮説がどの程度正しいかを検証するために最も効果的なデータリクエストシートを作成します。必ず開示を依頼するデータ・資料も相当数ありますが、事前に精度の高い仮説を持っておくことで、効果的な情報収集を行うことが可能になります。
3. 開示資料の分析
人に関する重要な情報は、デューデリジェンスの早い段階では、中々開示されないことも少なくありません。案件が成立しなければ機密情報を単に社外流出させたということにもなりかねませんので、売り手側としては慎重になるので当然です。初期の段階は、断片的な開示情報を繋ぎ合わせ、インタビューへ備えることも多いものです。
4. ファイナンシャル・アドバイザーを通じた質疑応答
データルームへの情報開示が始まると、対象企業との質疑応答も始まります。書面による場合と直接インタビューができる場合がありますが、経営幹部と人事責任者へのインタビューは必須事項です。断られても粘り強く依頼を行います。質疑応答でも、より速く欲しい情報を得るためのテクニックがあります。
5. マネジメント・インタビュー
人事役員を含む経営陣へのインタビューでは、経営者の観点に立ってインタビューを進めます。デューデリジェンスの場面とはいえ、会話の中で「同じ人事に携わるプロ同士であるという共感」が生まれるとインタビューも円滑に進みます。細かい話に入る前の段階で、この状態に入るための工夫を凝らします。
6. 情報の分析と報告書の作成
開示資料とインタビューで収集した情報を整理・分析し、クライアント企業の戦略を踏まえた上で報告書を作成します。報告書は、買収価格に影響を与える項目とそれ以外の定性的な項目に分けて行うことが一般的です。
※上記は標準的な進め方のイメージです。案件により、幹部社員層へのインタビューを実施する場合や人件費のプロジェクション支援を行うこともあります。
基本サービス内容(社員転籍プロセス支援)
価値を生み出す資産である「ヒト」の円滑な転籍を支援します
M&Aのストラクチャーによって必要となる雇用契約の移管
人材の円滑な転籍と定着で、PMIシナリオの前提条件を確保する
 デューデリジェンスが終了し、その後の交渉が順調に進めば、M&Aの基本合意からクロージングへと進みます。多くの場合、買収する会社の社員は、買い手企業が引き継ぎますが、M&Aのスキームによっては、社員個人から転籍に関する個別同意書を取得することが必要になります。転籍とは、これまで雇用されていた会社との雇用契約を終了すると当時に、新しい会社との雇用契約を結ぶという行為を並行して行うことを意味します。
デューデリジェンスが終了し、その後の交渉が順調に進めば、M&Aの基本合意からクロージングへと進みます。多くの場合、買収する会社の社員は、買い手企業が引き継ぎますが、M&Aのスキームによっては、社員個人から転籍に関する個別同意書を取得することが必要になります。転籍とは、これまで雇用されていた会社との雇用契約を終了すると当時に、新しい会社との雇用契約を結ぶという行為を並行して行うことを意味します。
事業譲渡として会社を買収する場合、転籍予定の社員全員から、個別に転籍同意書を取得するための実務作業が発生しますが、極めて短期間で、またM&Aの状況によっては、相当の人数が転籍対象となるため、実務的なワークロードは瞬間的に極大期に突入します。
転籍後の人事処遇内容が、全く同じであったとしても、会社の看板が変わったり、経営陣が入れ替わるなど、必ずしも働く環境が全く同じであるとは限りません。さらに、転籍した後に、いつまで転籍時の処遇の前提が継続されるかも不透明感を払拭しきれません。
第一ステップは、円滑に転籍予定の人材に新会社へ転籍してもらうことですが、当然、それはゴールではなくスタートラインに立ったということに過ぎません。その後如何に長く会社に定着してもらえるよう工夫をするか、以前と同じようなモチベーションを維持して職務に励んでもらうか、対応の手を緩める時間はないと考えた方が無難でしょう。
社員転籍プロセスの進め方と留意点
当事務所では、クライアント企業の状況に応じて、社員の転籍プロセスの設計、新処遇内容の設計、コミュニケーションプランの立案、面談への同席等を支援しています。ここでは、事業譲渡時における社員転籍の標準的な進め方をご紹介します。
1. 全体スケジュールの設計
M&Aでの転籍は、とにかく時間との戦いです。通常であれば、親会社から処遇水準の低い子会社へ転籍する場合など、労働組合との交渉期間も含めて相当長期間をかけて、転籍プロセスを進めることもありますが、M&Aではその数倍のスピードが求められます。当事務所は、人事アドバイザーとしてデューデリジェンスの段階から支援しているケースが多いので、すでに入手・分析済みの情報も活用し、転籍実務のスケジューリングを、実際のリソース対応面も含めて立案します。
2. 買い手 VS. 売り手の人事処遇比較
M&Aの状況下での転籍は、多くの場合「全体として同等の人事処遇を、一定期間、維持する」という条件がつきます。社員の雇用を維持したいという売り手企業の配慮からですが、人事処遇を全く同じにできるかというと、実際にはできないことも少なからず存在します。そういった事項を一つ一つ洗い出し、対処策を立案・クライアントとの討議を経て、転籍オファーレターに記載する条件を決定していきます。
3. Transition Service Agreement (TSA)交渉の支援
新旧の人事処遇内容の格差が明らかになったところで、その格差を埋める手段がない場合、売り手企業に対して、一定期間、サービスを継続提供してもらえるよう交渉を行います。これをしないと、クロージング以降、転籍してくる社員が不利益を被りますし、あるいは、転籍の合意をしない社員が出てくる可能性もあります。健康保険組合や企業年金、共済会などがTSA交渉の対象となることが多くあります。
4. 転籍対象者への個別面談
申し入れる人事処遇内容を固めた後は、対象者との個別面談へ進みます。一定規模以上の事業会社が買い手の場合は、事業部門長や人事部門が個別面談を実施しますが、中小規模の会社や投資ファンドが買い手の場合、外部アドバイザーとして面談に同席して処遇内容の説明を支援する場合もあります。
※上記は、基本的な処遇条件を維持する方針の場合の進め方のイメージです。案件により、転籍後の処遇条件が下がることを前提に、転籍時に支給する転籍促進のための特別な処遇を設計支援することもあります。詳しくは、お問い合わせください。
人事制度統合支援
PMIの経営・人事方針を踏まえた新人事制度を設計、導入を支援します
「人事戦略の策定」と「期待する人材像の明確化」が成功への出発点
人事制度を「くっつける」だけでは、上手くいきません
 統合というと、文字通り、制度を合体させることを想像されるかもしれません。しかし、両制度のいいところを足して二で割っても、上手くいかないのです。経営者の考え方や人事方針との一貫性がなくなり、日々の運用を重ねていく中で綻び、ヒトの力を充分に引き出すことができなくなります。当社では、新会社の経営方針を踏まえ、人事に関する戦略を明確にすることを重視します。これが明確になれば、「どのような人材を、どのように採用・育成し、処遇するのか?」という人事制度の根幹がぶれなくなります。人事戦略と人材像を明らかにすることで、採用基準や異動・配置、人事評価から育成等々、人材マネジメントのあらゆる面に筋を通すことができるのです。
統合というと、文字通り、制度を合体させることを想像されるかもしれません。しかし、両制度のいいところを足して二で割っても、上手くいかないのです。経営者の考え方や人事方針との一貫性がなくなり、日々の運用を重ねていく中で綻び、ヒトの力を充分に引き出すことができなくなります。当社では、新会社の経営方針を踏まえ、人事に関する戦略を明確にすることを重視します。これが明確になれば、「どのような人材を、どのように採用・育成し、処遇するのか?」という人事制度の根幹がぶれなくなります。人事戦略と人材像を明らかにすることで、採用基準や異動・配置、人事評価から育成等々、人材マネジメントのあらゆる面に筋を通すことができるのです。
「我」の衝突を包み込み、新たな企業文化を創造する
両社の力関係に格差がない場合、出身会社による「我」の衝突が起こりがちです。人員配置はその最たるものですが、人事制度でも、両社の同期入社者の賃金水準や格付けに配慮することがよくあります。パフォーマンスの最大化や適材適所の観点からは、効率が悪いように見えますが、和を重んじる日本の組織では、一定期間、このような措置を講ずることも、一概に悪いこととは言い切れない部分もあります。M&Aの人事統合では、型通りの正解は存在しませんが、当社では、日本的な要素も尊重しつつ、統合効果実現のスピードと人心の融合のバランスを重視したアドバイスを基本スタンスとしています。
統合プロセスの設計が、人事統合の成否の分かれ目です
 すばらしい制度設計をしても、統合のプロセスに配慮がなければ、事はうまく進みません。制度設計のプロセス自体に社員を巻き込み、当事者になってもらうと同時に、職場での変革をリードしてもらう仕掛けも必要です。社員の不安に答える組織的なコミュニケーションを通じて人材の流出を防ぎ、組織力を維持したまま、統合前後の期間を乗り切る必要があります。当社では、幹部社員層に当事者意識を強く持ってもらうように働きかけ、配下の社員のモチベーションマネジメントを含めて、社員の一体化を促進する観点から支援を行っています。
すばらしい制度設計をしても、統合のプロセスに配慮がなければ、事はうまく進みません。制度設計のプロセス自体に社員を巻き込み、当事者になってもらうと同時に、職場での変革をリードしてもらう仕掛けも必要です。社員の不安に答える組織的なコミュニケーションを通じて人材の流出を防ぎ、組織力を維持したまま、統合前後の期間を乗り切る必要があります。当社では、幹部社員層に当事者意識を強く持ってもらうように働きかけ、配下の社員のモチベーションマネジメントを含めて、社員の一体化を促進する観点から支援を行っています。
基本サービス内容(人事制度の統合支援)
経営戦略と連動した人事戦略を可視化し、新社最適の人事制度の統合を支援します
M&Aの人事制度統合は、技術的な制度統合以前に戦略整合性が重要
新社戦略との連動を確保し、客観的な基準による格付けと処遇の実現が成功の鍵
 M&Aの中でも特に合併の場合は、人事制度の統合の巧拙が、社員のモチベーションに大きく影響します。会社は独自の企業文化を形成していますが、合併を機にそれが変わります。企業文化とは、会社として実践を奨励する有形無形の価値基準です。合併でそれが変わります。会社の価値基準が変われば、その実践度の向上を促進するための人事制度の仕組みも変わります。
M&Aの中でも特に合併の場合は、人事制度の統合の巧拙が、社員のモチベーションに大きく影響します。会社は独自の企業文化を形成していますが、合併を機にそれが変わります。企業文化とは、会社として実践を奨励する有形無形の価値基準です。合併でそれが変わります。会社の価値基準が変われば、その実践度の向上を促進するための人事制度の仕組みも変わります。
特に重要となるのが、資格等級制度における社員の格付けです。資格等級制度は、客観的な基準に沿って社員を序列化するものということができますが、統合新社が、どういう基準で社員を格付けするかは、社員にとって大きなメッセージとなります。また、奨励される組織運営の方法や行動規範が変われば、人事評価の観点も変わります。そして、貢献に対する報酬の考え方が変われば、報酬制度も変わるのが自然です。
合併する各社の人事制度を比較して、パズルを合わせるように組み合わせるだけでは、辻褄合わせに過ぎません。そのような統合新社との戦略整合性がない人事制度は、出身各社のメンツを維持することは可能かもしれませんが、経営ツールとしての機能性は、とても低くなってしまいます。同時に、社員にとっても、将来の成長とキャリア形成が、会社の成長や方向性とずれてくる可能性も大きくなります。
当事務所は、統合新社の経営戦略を踏まえて人事戦略とあるべき人材像を可視化することが重要と考えます。その上で、適切な基準によって社員の格付けを行い、求める人材が効率的に育ち、かつ、期待する貢献を達成した社員が適切に報いられる仕組みの構築を支援します。この一連のプロセスを経て、出身会社間の競争という意識レベルを脱し、新社最適・未来志向の組織風土が醸成されることを支援します。
人事制度統合の進め方
人事制度の統合について、ここでは、M&Aで特に重要となるポイントについてご紹介します。なお、人事制度設計の技術的な進め方に関しては、「資格・等級制度の設計・導入支援」、「評価制度の設計・導入支援」、「報酬制度の設計・導入支援」をご覧ください。
1. 人事戦略の可視化と共有
統合新社の経営戦略を踏まえた人事戦略の可視化は、合併の場合は極めて重要です。このプロセスを抜きにして、人事制度の統合作業に入ることは考えられません。合併では、出身会社間の綱引きが起こりがちですが、当事務所は、第三者のアドバイザーとして、新社最適の視点から、統合議論をリードします。
2. 統合新社が求める人材像の可視化
会社には、暗黙のうちに奨励されている行動形式やものの考え方があります。合併会社の社員が同じ職場で働きだすと、それは顕在化してきます。当事務所では、人事制度の設計に入る前の段階で、意識的にそのギャップを可視化するために、ワークショップを実施します。
3. 統合新社での格付け基準の明確化
可視化された人事戦略とあるべき人材像を踏まえて、具体的な人事制度の統合議論に入ります。あるべき人材が、適切に処遇され、効率的に育成されて会社に貢献することができるための基準は何か、という観点から、社員を格付けする際に観点を決定していきます。
4. 統合新社の評価基準の明確化
あるべき人材像を明確に意識して、行動評価の観点を検討します。また、統合の初期段階においては、様々な統合イニシアティブがプロジェクトとして運営されるため、通常業務に加えて、統合プロジェクトワークに対する評価方法も含めて、社員の貢献が適切に反映されるように評価の仕組みを検討します。
5. 評価と報酬の連動方法の設計
人事評価と賞与・昇給・昇格の連動方法は、会社の方針がストレートに現れる部分です。評価による処遇格差をどの程度に設定するのか、固定報酬と変動報酬の割合をどうするのか等、あくまでも新社の戦略に沿った仕組みの構築を可能な限り追求します。たまたま合併各社の仕組みがほとんど同じであっても、新社の戦略整合性の観点からの検討は欠かさずに実施します。
6. 移行措置の検討
新社の資格等級制度による格付けや報酬制度の変更に伴い、処遇水準が上がる社員と下がる社員が発生することは避けられません。労働法を踏まえた適切な移行措置を設定することは最低限の必要条件です。その上で、周到に準備されたコミュニケーションを含むチェンジマネージメントを通じて、人事制度の移行に伴うプラス面の影響を最大化し、マイナス面の影響を最小化する工夫を支援します。
※上記は合併を前提とした場合の人事制度統合に伴う主な論点です。詳細につきましては、どうぞお気軽に下記までお問い合わせください。
統合組織診断
組織の相性も踏まえ、アクションプランをともに考えます
M&Aの目的を実現するため、定期的な組織診断の実施が効果を発揮します
M&A実施前の組織診断で、生産性の低下を防ぐ
 M&Aを実施した直後は、ビジネスプロセスや組織運営の統合をはじめ、顧客対応も含めて様々な対応が求められるため、通常時にも増して、社員が一丸となって対応する必要があります。しかし現実には、新組織での組織運営・人員配置や金銭・非金銭面の処遇を含めて、不確定な要素が残っていることも少なくなく、社員の一体的な取り組みが阻害され、一時的に生産性が低下する現象がみられます。極めて限られたM&Aの時間軸の中で、組織診断を通じて、組織・人事面の優先課題を把握し、対処することは、統合前後の生産性の落ち込みを最小化し、最短距離で成長軌道に乗せるために効果的なアプローチといえます。
M&Aを実施した直後は、ビジネスプロセスや組織運営の統合をはじめ、顧客対応も含めて様々な対応が求められるため、通常時にも増して、社員が一丸となって対応する必要があります。しかし現実には、新組織での組織運営・人員配置や金銭・非金銭面の処遇を含めて、不確定な要素が残っていることも少なくなく、社員の一体的な取り組みが阻害され、一時的に生産性が低下する現象がみられます。極めて限られたM&Aの時間軸の中で、組織診断を通じて、組織・人事面の優先課題を把握し、対処することは、統合前後の生産性の落ち込みを最小化し、最短距離で成長軌道に乗せるために効果的なアプローチといえます。
M&A実施後の組織診断で、強い組織を作る
M&Aによる効果は、財務諸表から把握できるものと、出来ないものがあります。特に雇用調整や配置転換を行った場合、短期的なコスト構造の改善により利益が上がったとしても、持続的な成長が約束されたことにはなりません。一般的に、M&A後1年以内、すなわち、どのような人事処遇が行われるのかが見えてきた段階で、退職リスクが高まったり、出身会社別の行動パターンの違いから、組織内に不協和音が広がっている場合があります。M&Aの前後で組織診断を実施した・しないに関わらず、統合1年を目処に実施することが目安です。この段階での組織・人事課題の把握と対応が、その後の成長を支える強い組織をつくれるかどうかの分かれ目といえます。
就業規則の統合支援
対等合併、片寄せ、JV、あらゆるM&Aでの統合経験があります
M&Aにおける就業規則の統合は、両社の歴史に対する配慮も必要
モデル就業規則を元に、新しい規程をつくることのリスク
統合新社の就業規則について、「モデル規程を元にして作成してほしい」という依頼を受けることがあります。このアプローチでも規程を作文することはできますが、お薦めはしていません。なぜなら、就業規則は、その会社の長い営みの中で積み上げられてきた労使間のルールの集大成だからです。これらを丁寧に取り上げ、相手の規定内容と突き合わせる地道な作業をしないと、お互いの会社を知り合うというプロセスが抜け落ちるため、運用を重ねるに従い、不備や亀裂が生じる可能性が大きいのです。統合新社の経営方針により、統合方針が明らかであれば、どちらかの規程に合わせることを前提に、必要な調整を施すことで問題ない場合もありますが、そうでない場合は、留意が必要です。
両社の歴史とビジネスプロセスの違いを踏まえ、統合作業をリードします
当社では、専門家の見地から、両社の就業規則を技術的に統合することにとどまらず、「なぜ、このような規定内容になっているのか?」について、ディスカッションを通じて、詳しくヒアリングを行います。議論の過程で、暗黙のルールとして存在していたものが明確化されたり、人事検討チームの一体化が促進されるなどの効果を、実践で検証済みです。実際の統合作業では、人件費、コンプライアンス、人材マネジメント、アドミンの観点から徹底的に検証すると同時に、人事戦略、人事制度や新社のビジネスプロセスとの関連性も踏まえ、最終的に新社の経営の想いを入れるところまで支援を行います。
基本サービス内容(就業規則の統合支援)
行間に内在する労使関係の歴史も踏まえ、新社最適の就業規則の統合を支援します
就業規則単独の議論ではなく、人事制度の統合を踏まえた検討が必要
統合各社の労使関係、人事諸制度との連動、各社の就業形態の違いを押さえる
 就業規則の内容は会社により異なります。条文内容が異なるのはもちろんのこと、規程の構成において次元が違うレベルの格差が見られることもあります。日本の上場会社が分社化した上で、外資系企業の日本法人と合併する場合などが、その一例です。
就業規則の内容は会社により異なります。条文内容が異なるのはもちろんのこと、規程の構成において次元が違うレベルの格差が見られることもあります。日本の上場会社が分社化した上で、外資系企業の日本法人と合併する場合などが、その一例です。
日本の伝統的な上場企業は、労働協約で合意している労働条件、資格等級、評価、賃金表を含む報酬等に関する人事処遇のほぼ全てを、就業規則に記載していることが少なくない一方、外資系企業の就業規則は、一般的に、処遇内容については比較的簡素な情報しか載せていません。
日本の企業同士が合併をする場合でも、就業規則および付属諸規程で定める就業条件、福利厚生などは、両社の条文を並べて、上手く一つの文章にまとめるという作業でないことは言うまでもありません。会社固有のビジネスプロセスに適した就業条件が日々のオペレーションの中で磨き上げられ、それが規程にも反映されています。就業規則の統合を進めるためには、統合新社のビジネスプロセスやそれを支える人事制度との連動を意識する必要があります。
しかし現実の合併人事統合の現場では、人事制度統合チーム、退職金統合チーム、就業規則統合チーム、福利厚生統合チームという具合に、会社の組織構成に沿ったチーム編成が行われるため、チーム間のタイムリーかつ抜けもれのない情報の共有が困難になるという難点があります。
全体として一つである人材マネジメントの総体を部分に分けて同時並行で進めるため、結果として、検討中の制度内容や規程を持ち寄った時に、うまくかみ合わないということが起こります。これを最小限に抑えるためには、横串を通して全体をコントロールする機能が必要です。
しかし、スケジュール管理のみをするようなプロジェクトマネジメントでは不充分です。全ての領域に精通したスペシャリストが、自律的に、常に2歩、3歩先の展開を見通して、予想される問題を共有し、手遅れになる前に検討するべき課題を担当チームに割り振るということが求められます。
当事務所は、労働法の専門家の立場から就業規則の統合を支援することはもちろんのこと、統合新社のビジネス戦略から規定される社員の働き方や人事制度上の人件費インパクトまで含めて、包括的な観点からの支援をご提供いたします。
就業規則統合の進め方
ここでは、日本企業同士の合併を前提として一般的なプロセスについてご紹介します。
1. 就業規則の比較表作成
合併各社の就業規則の比較表を作成し、会社間の共通点、相違点を洗い出します。留意点は、福利厚生に関する項目です。福利厚生に関する項目は、個別の条文ごとに比較しても木を見て森を見ずの典型的な状況になりますので、注意が必要です。
2. 就業条件格差の洗い出し
比較表が出来上がったら、各社間の条件の格差を確認し、その時点で把握できている関連領域の統合方針などを踏まえて、就業規則の統合の方向性を仮説ベースで検討します。
3. 就業規則制定の経緯の理解
就業規則の統合の仮説を構築することと並行して、各社の就業規則の内容が、なぜ現在の形に至ったのか、可能な限り、過去の労使協議の内容なども含めて、議論の中でヒアリングを行います。住宅に関する規定などは、特に留意が必要です。
4. 人事諸制度と連動した検討の実施
さらに並行して、人事制度の設計に直接関連する項目について統合の方向性を検討します。時間外労働関連の項目、就業時間の違いや裁量労働制、事業場外のみなし労働時間制の適用の有無などを検討します。人事制度の設計の方向性を充分に踏まえた上での検討が必要です。
5. 移行措置の検討
合併に伴う就業規則の統合では、将来の期待される権利まで含めて、全ての社員の条件が良くなることは考えにくい状況です。したがって、一定の確率で一部の社員の労働条件が同等以上に維持されないことが想定されます。こういった変更をできるだけ円滑に行うための移行措置の検討を行います。
※上記は合併を前提とした場合の一般的な検討ポイントです。詳細につきましては、どうぞお気軽に下記までお問い合わせください。
基本サービス内容(福利厚生制度の統合支援)
多種多様な福利厚生制度について、新社最適の観点から統合を支援します
人事制度統合とは異なるアプローチが求められるM&A時の福利厚生の統合
統合新社に残す制度、廃止する制度を選別し、費用対効果の向上を図る
 福利厚生制度は、大雑把に言うならば、社員の健康の増進と福祉の向上、および、一体感の醸成に資するべきものです。これを実務レベルで見ていくと、住宅に関する補助、事故や災害など生活のリスクに対する備え、健康増進施策、慶弔関連の給付、育児・介護支援、各種の特別休暇等、多くの制度・仕組みが様々な形で導入されています。
福利厚生制度は、大雑把に言うならば、社員の健康の増進と福祉の向上、および、一体感の醸成に資するべきものです。これを実務レベルで見ていくと、住宅に関する補助、事故や災害など生活のリスクに対する備え、健康増進施策、慶弔関連の給付、育児・介護支援、各種の特別休暇等、多くの制度・仕組みが様々な形で導入されています。
非常に多くの福利厚生制度について、費用対効果の観点から適切な統合をしていくためには、個別の制度毎の検討に入る前に、福利厚生領域全体の統合方針が明確でなければ、継ぎはぎの福利厚生制度が出来上がってしまいます。
先に挙げた住宅施策を強化するのか、あるいは住宅施策を縮小し、原資を給与に回すのかなど、福利厚生制度内のメリハリのつけ方や人事制度との連動も含めた統合の方向性を明確にすることが、最短距離で効果的な統合案を立案することに繋がります。
当事務所は、統合新社の人事戦略と整合性の高い福利厚生統合方針の立案段階から支援を行います。また、福利厚生領域に限定された議論ではなく、人事戦略、人事制度、雇用方針など、包括的な観点を踏まえた上で福利厚生を検討するため、福利厚生領域内での部分最適の統合に陥ることなく、全体としてバランスの良い人事統合の実現を支援致します。
福利厚生制度統合の進め方
ここでは、M&A時の福利厚生の統合について、一般的なプロセスをご紹介します。
1. 人材マネジメントにおける福利厚生の位置づけを明確化
会社によって福利厚生に対する取り組み姿勢は、相当異なります。統合新社として、人材マネジメントツールの一つとして福利厚生をどのように位置づけるのかについて、大きな方針がなければ、議論が迷走するリスクが高まります。当事務所では、大方針の策定段階から支援を行います。
2. 統合新社の福利厚生方針の明確化
福利厚生をひとつの領域とすれば、その中に様々なサブ領域があります。住宅施策、育児・介護、従業員保険、健康福祉、慶弔関連、貯蓄、レクリエーションなどのサブ領域のレベルで、何を強化し、リソースを重点的に投入するべきか等、福利厚生内の方針を定めます。
3. 福利厚生制度の比較・統合案の検討
統合する各社の具体的な福利厚生制度を比較し、統合案を検討します。この段階でハイレベルなコスト、移行措置の必要性、労組の反応など、主要な課題をまとめ、統合へ向けた検討を重ねます。
4. 利用頻度の確認とコスト分析
上記の統合案の検討と並行して、現状の制度の利用状況と会社が負担しているコストを試算します。現行制度の利用頻度が高い場合や、統合新社で当該制度を変更することが想定される場合は、社員へのコミュニケーション方法も含めて検討を重ねます。
5. 移行措置の設計
福利厚生領域においては、既得権と将来受給するはずであったという期待権の両面から、移行措置の内容を検討します。また、会社が直接コストを負担しているものや機会を提供しているだけのものなど、その仕組み毎の性質を踏まえた措置とコミュニケーション内容を、適宜検討していきます。
※上記は合併を前提とした場合の一般的な福利厚生の統合プロセスです。詳細につきましては、どうぞお気軽に下記までお問い合わせください。
基本サービス内容(健康保険組合の統合・編入支援)
保険料、給付内容、財政状況を踏まえた健保組合の統合・編入を支援します
会社の福利厚生、民間保険による給付も踏まえた健保統合議論が必要
健保組合の保険給付、保健事業だけの統合検討では部分最適に陥るリスク
 全国の健康保険組合の約8割が赤字決算という状況は、将来に渡って改善する状況は見られません。これまで別途積立金を取り崩して決算を凌いできた健保組合も少なくないと思われますが、近年は保険料の増額改定をするケースが目につきます。
全国の健康保険組合の約8割が赤字決算という状況は、将来に渡って改善する状況は見られません。これまで別途積立金を取り崩して決算を凌いできた健保組合も少なくないと思われますが、近年は保険料の増額改定をするケースが目につきます。
また、総報酬割制の導入議論が進められており、近い将来、給与水準の高い企業にとっては、高齢者拠出金などの負担がさらに膨らむシナリオも想定されます。このような状況において、M&A時の健保組合の合併・編入に関する検討の巧拙は、会社の将来人件費に小さくない影響を及ぼします。
複数の会社が統合する状況では、統合新社として加入し得る健保組合が複数あり得ます。当事務所は、加入可能性のある健保組合について、保険料、給付面の検討はもちろんのこと、財政面の検証まで含めた総合的な分析を通じて、最適な健保組合への統合・編入を支援します。
健康保険組合の統合・編入の進め方
ここでは、M&A時の健康保険組合の統合・編入について、一般的なプロセスをご紹介します。
1. 現状分析
会社の合併に伴い、健保組合も合併する場合は、存続健保組合を決定するための諸論点の洗い出しから、保険料、給付、保健事業の比較検討を行います。比較検討に際しては、会社直接給付の類似の給付や民間保険会社に付保している給付なども含めて、全体像を踏まえた比較分析を行います。
2. 編入する健保組合の検討
統合各社の健保組合を合併するシナリオに加えて、必要に応じて、総合型の健保組合や協会健保へ編入の可能性も含めて、保険料、給付、モチベーション、アドミンなどの観点から検討を行い、有力なシナリオに絞り込みます。
3. 健保組合の財政検証
合併健保組合、あるいは、買収側の会社として編入したい健保組合を見定めた段階で、入手可能な情報から可能な範囲で、健保組合の将来保険料のコストを試算します。年度別の必要保険料コストと保険料増額改定の必要性の程度を確認し、許容範囲の場合、案を確定します。
4. 移行措置の設計
保険料負担が上がる場合、必要に応じて、急激に負担が増加しないようにするための移行措置を検討します。移行措置を設ける場合、健康保険料を単独で捉えると移行コストが膨らむ可能性があるため、人事制度やその他の福利厚生の改訂とも合わせて、包括的な移行措置を検討することも視野に入れます。
※上記は一般的な健保組合の統合・編入プロセスです。詳細につきましては、どうぞお気軽に下記までお問い合わせください。